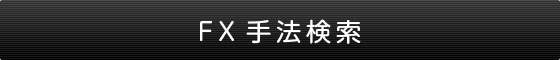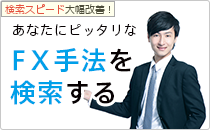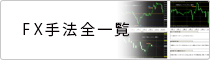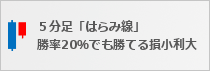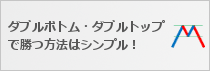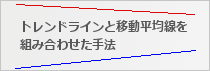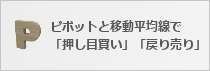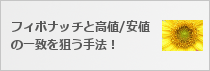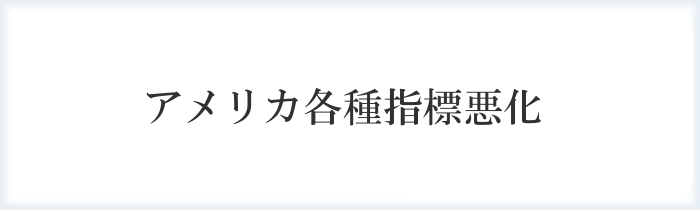
きのうのアメリカの各種指標は、まだイギリス離脱の影響が出ているのか、と思うような内容であった。一番、驚いたのは「卸売物価の下落」に個人的にはなります。
また各連銀の指標に関しては各地区の連銀総裁のコメント通りの指標が出たな、と感じる次第です。
現況のアメリカ経済は、ドル安に誘導していますので物価は本来上がらなくてはいけない、ということが第一の前提にあります。
具体的にいうと日本では、円安に誘導をすると輸入物価が上昇し、国内の物価が上昇する、というのが日本政府、日銀の思惑です。そうすれば税収、消費税の税収は増えるのは誰でもわかる話だと思います。
つまり、アメリカドルが実力以上にドルが買われていることがアメリカ経済を下押ししていると「イエレン議長」が考えていることがあり、2015年年初からドル高の是正を求めています。
これで、国内の物価を押し上げれば「デフレ」懸念の払しょくになり、引いては物価が上昇すれば賃金も上昇し、景気拡大の循環に入るというのは基本的な考え方です。
ところがドル円相場をみればわかる通り、ドルは対円で年初から20パーセント弱、下落をしているのにも関わらず全く、アメリカの物価は上がらず、逆に下落をしてしまった、というのは「FRB」にとっては重大な関心事です。
そもそも「QE」というのは「デフレ」退治、「デフレ」経済の循環に陥ることを防ぐために前議長の「バーナンキ」が導入したものですが、ここを勘違いする人が何人もいらっしゃるのですが、2014年10月に「QE」を停止したのではなく、「QE」の「拡大」を停止しただけの話であって、現在も「QE」は継続中ということです。
「QE」導入の目的が「デフレ」脱却のためであれば、今回の卸売物価指数の低下は労働市場拡大、賃金上昇などの景気拡大局面では通常は起こり得ないことなのに起こってしまったのは、「FRB」にとって非常に頭が痛いことになると思います。
これを「イエレン議長」や「オバマ大統領」が行っている施策になりますが、現代はインターネット技術の派生によって供給が大幅に増加をしてそれに対して需要が追い付かないという状態にあるのか、どうなのかを考えるのが「FRB」の判断です。
もちろん、従前から私が言っているように、この状態で9月の利上げなど考えようもなく、例によって12月にアメリカが利上げするのは規定路線のような気がします。
では、これを否定する考え方というのは、結局、イギリスのEUからの離脱決定をうけて資本がイギリスから逃げて、ドルやユーロに流れ込んだ資本が、未だ活用されていないことが招いた経済活動の停滞と考えるのであれば、何れレパトリをしたポンドのマネーは活用されるので年末には景気がよくなると思います。
しかし、最悪のシナリオとして、年末までにアメリカ経済が回復をしない場合のシナリオを今回の指標発表で考えておかなければいけないのかな、と考えている最中ですが、依然として私の考え方は年末までには「アメリカ経済は回復をする」のが個人的な考え方になります。
(この記事を書いた人:角野 實)