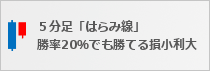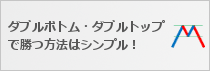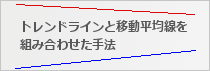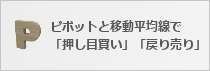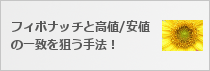先に上海合意によって、中国の国際的な救援プログラムが発足したという説明をしてきました。
その上海合意が2月の末になるので、月末の売りをこなしながらもアメリカの株価を中心に上昇をしてきているのが現在の状況になります。
日本株を海外勢中心に売り
3/7の週に外国人投資家が大量に売り浴びせています。これは私が懸念をしていた日本の「デフレ化」に対応するポジションだと推察されます。日本銀行の企業物価が3/10に発表されています。
⇒ http://www.boj.or.jp/statistics/pi/cgpi_release/cgpi1602.pdf



上記の数字をみると本格的に日本は「デフレ化」しそうな数字になります。
ここ最近、「安倍首相」が消費税増税を先送りにするために一生懸命やっていますが、個人的には消費税というのは結局、消費すれば罰金を取るような税金ですので消費が盛り上がるわけがないと思っています。この数字をみれば消費税増税などできるわけがありませんよね。
相変わらず、老害といっても過言ではない「内閣府参与」がまたクルーグマンと組んで本を出版しています。老害の内閣府参与は「もういい加減にししたまえ」という人がいないのでしょう。
彼が提言したことはすべて失敗に終わっていますし、「前日銀総裁の白川氏」をボロクソにいっているのは愉快ではありませんし、デフレの正体の藻谷さんにも謝罪したのでしょうか?
消費税増税を見送る時点でもうすでに、「アベノミクス」は失敗といっているようなものです。
なぜなら、東日本大震災直後に当時の首相、野田さんが「このままだと日本はギリシャになってしまう」という言葉通り、「アベノミクス」は財政危機に対応するための政策です。
格付け会社からの日本国債の格下げを回避するためにやったので税収不足を散々指摘されているのを、それを否定する政策を発表しようとする自体が失敗ですね。私が再三言うように「アベノミクス」は失敗するよ、と言ったことが現実になる一歩手前でしょう。

ドイツのおかしさ
去年、私はドイツが今度は危機に陥るよと予言をしたと思います。案の定、ドイツのおかしさが明らかになってきました。
ドイツ人の韓国嫌いは有名な話なのですが、日本のこともあまり好きではありません。その根拠というのはドイツ人というのはもともと、ルールを厳格に守ることを重視する民族だからです。
つまり日本の財政規律は借金を野放図に垂れ流してなんて、だらしがない民族なのだというのは日本のバブル崩壊から言われていることです。
日本のことをあれだけ批判をしておいて政府債務は適正な水準ですが、単に政府出資の「ドイツ銀行」に債務を付け替えただけと非難されたら何も言えません。
しかし、このことは政府首脳や世界各国には既知のことになりますので、大した問題にはならないと思います。何度も言うように既知の危機というのは大した暴落にはなりません。一番問題なのは突然の危機がテールリスクになるのです。

上海合意はドル安と今年は心得るべきではないか?
かつてプラザホテルで合意をした「プラザ合意」は今回、「上海合意」としてドル安の合意として合意されました。日本やドイツが危機に陥っているのに、中国の危機の方が重要というのは世界の合意になります。ただし、通貨の世界は俗に三極と言われ、ドル、ユーロ、円で形成をされています。
この3つの通貨のうち、ドル安は世界で合意されているのですからドル安は確定です。このドル安で確定するものはアメリカ経済が好調という前提なら株は買いになります。
そしてドル安によって新興国、資源通貨は戻ります。原油を筆頭とした商品価格も以前から言うように戻りに入りますね。でも資源、新興国通貨、商品は長期では「戻り売り」だと思います。単なる戻りと個人的には考えています。

この辺りがみなさん理解できない方が多いのですが、世界の為替取引の40パーセント以上はユーロドルになりますので、ドルが安ければユーロが高いのは当然です。
上記のドイツの問題にフォーカスを当てるとユーロは安くて当然とか言う人は基本を理解していないと思います。経済と政策がどちらが優先をするのか、よく考えてもらいたいのです。
そして日本円に関しては、円高でも円安でもフリーハンドになるのです。ただし、円高の場合はユーロ高、円高になりますので、その効果はドルが相当安くならなければなりません。
円安の場合はドル安、円安になりますので、ユーロが急騰するということになる図式があまり理解できないようです。上記2つのケースを考えると円高のほうが国際合意を背景になる可能性は高いのです。
ユーロ高も、ドイツやギリシャの問題を内包するユーロもあまり現実的ではないのですが、円高の方がまだ可能性は高いと思うのです。
ただ、今年一番動くのはドル円よりもユーロドルなのだと理解すればいいのですが、このことを理解できる人は少ないようですね。
(この記事を書いた人:角野 實)